
木曽もめっきり寒くなって来ましたね。
カメムシの越冬目的での家内侵入が増加中の今日この頃です。
さて、今回は大桑村で創業100年を越え、現在は神社仏閣の屋根板製作を主な仕事とされている木工会社「栗山木工有限会社」さんを紹介させて頂きます。
1912年に創業者の栗山喜三郎さんが三重県より木曽の良材(天然サワラ)を求め大桑村で屋根板製作の会社をはじめ現在に至ります。「とんとん葺き」「柿葺(こけらぶき)」とも呼ばれる屋根瓦の下に重ねられている屋根板木材の加工を専門に仕事をされています。なんと国内で専門的に柿葺板を製作出来るのはもう4社程しか無いそうです。出雲大社、伊勢神宮、金閣寺、銀閣寺をはじめ、国の重要文化財の建造物の柿葺の屋根板を約樹齢300年以上の木曽の良質な天然サワラ材で製作されています。

栗山木工代表の栗山弘忠さんにお話を伺いました。
仕事場はきちんと整頓されており、凛とした空気と天然木の良い香りが漂っています。
丸太から柿葺のヘギ板になるまでの一連の作業を見せていただきました。栗山さんは家業を継ぎ今年で約25年になるそうです。丸太を順々に割っていくのですがその都度、木に向き合って実際に声に出して木にコメントしている姿に職人の心意気と仕事への愛を感じました。

仕事をされている時は迂闊に話しかけられない空気をまとっているのですが、いざお仕事についてお伺いするととても丁寧に気さくに、ざっくばらんに話していただけました。国の重要文化財の材を納めるという、技術も覚悟も必要な仕事だけど、楽しいよ。と素朴に語っていたのが印象的でした。
次の100年を見据えて後継者の育成にも力を入れているそうです。現在は高木 諒さん、木戸 智裕さんの2人の若き職人さんが伝統技法を継承されています。お二人とも10年程働かれており、すでに作業の所作、オーラにとても貫禄があります。


このkisokurashi で紹介するにあたり栗山さんとも木曽の移住の現状ついてもお話ししました。栗山木工も後継者育成には力を入れたいとのことですが、生活面で考えると病院の問題、人口減少にともなう学校や子供の習い事、教育の維持等の諸々の問題が実際にあるので、なかなかどうぞ是非とも木曽に、大桑村に来て下さいとは言えない所も多々あるとのことでした。僕も同感です。
ですが、この仕事はここでしか出来ないので栗山木工の仕事の魅力で来てくれる人が居れば嬉しいともおっしゃっていました。全国的に人口減少、過疎、問題は山積みですが谷底の木曽文化は平地が少ないお陰か、ショッピングモールが出来たり下手な開発もあまり進んでいないのでまだまだ木曽には貴重な伝統文化が残っています。栗山木工さんのように向こう100年を見据えた仕事というのはとてもカッコ良いなと思います。まだまだ柿葺の伝統技術はAIには取って代わられないのではないでしょうか。


僕も大桑村で「大桑焼」と勝手に名付け縄文人ぶりに村の土を使い焼き物を作っています。薪窯でも作品を焼くので栗山木工さんにヘギ板を製作する際に出た端材を頂いております。燃やす時は樹齢200年以上の材ということで畏れ多いですがありがたく使わせていただいております。
僕も「大桑焼」初代で終わってしまうかも知れませんが、栗山木工さんのように次の100年も見据えれるよう、頑張っていきたいと思います。
文・写真 : 奥野 ( 岐阜→愛知→岐阜→メキシコ→大桑村 )






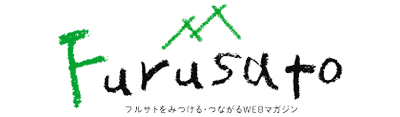





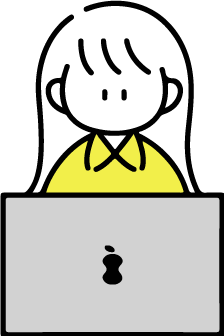 お問い合わせは
お問い合わせは